客演指揮者 秋山和慶先生 インタビュー
ー秋山先生と昔の京大オケー
学生指揮者:秋山先生が最初に京大オケを振ってくださったのが60年ほど前で、我々も歴史として聞いているところなんですが、当時の印象だったり、覚えていることはございますか?
秋山先生:古い木造の建物の講堂(学生集会所)で、冬でね、12月だったから、ものすごく寒くてね……。小さい石油ストーブみたいなのが2つか3つ置いてあるだけで、ラッパのやつなんか手袋の指先をちょん切ったようなのをつけてガタガタ震えながら練習してたね。
一同:(笑)
秋山先生:ホルンなんかもすぐ水がたまっちゃってね、皆苦労したのは覚えてるね。
学生指揮者:当時の記録を漁ってみたところ、演奏会の打ち上げもそろそろ終盤という頃に、突然部屋が暗くなり、怪人の仮面をつけた秋山先生が登場して騒然としたというエピソードが我々の方にも残っておりまして。
秋山先生:ほんと?全然覚えてないや。
一同:(笑)
学生指揮者:そのようなエピソードを見ても、楽しんでいただけたのかなという印象を持ちました。
秋山先生:あの時はね、ドヴォルザークのチェロ協奏曲をやったのは覚えてるんだけど。
学生指揮者:あとは、シベリウス交響曲第2番と、リェンツィですね。
秋山先生:相当ヘビーなプログラムだね。
学生指揮者:そうですね、しかもそんな寒い中で、なかなか大変な曲だと思いますけど(笑)
秋山先生:管楽器は、ちょっと休んでる間に水がたまったり、音程狂っちゃったり、音程合わせるだけでも大分苦労したね。
学生指揮者:その後だいぶ間が空いて、3年前の2021年6月に開催する予定だった定期演奏会でも客演指揮者を再びお願いし、引き受けていただいて曲が決まるところまではいったんですが、コロナ禍の影響で中止になってしまいました。そのあと実は2月か3月に延期しようという話もあったんですが、こちらの力不足でそれもできず……。あの時ご一緒できなかったのは本当に申し訳なかったなと。
秋山先生:コロナはね、どこのオーケストラも中止になったり、やったとしても奏者の間をこんなにあけたり、パーティションを管と弦の間に置いたり、皆それで遮断されちゃってさ。もしやったとしても悲惨なことになってたかもしれないよね。(笑)
学生指揮者:特に学生団体としての影響としては、だいぶ期間があいてしまって、その間に人の入れ替わりもあって、しかもそれで全然できていない状態で。秋山先生にお願いした次の演奏会からなんとか再開することができたんですが、かなりぎりぎりの状態で。それでもなんとか立て直してきて、色々と定着してきた頃にまたもう一度引き受けていただけたこと、本当に嬉しく思います。
秋山先生:3年前は、ああ残念だなぁと思っていたんだけど。でも今回これでようやく復活だなぁなんて思ってね、嬉しかったですよ。
学生指揮者:ありがとうございます。今回改めて指揮をお引き受けいただき、先月初めて直接ご指導いただいた際が本当に久しぶりの京大オケだったと思うんですが、以前振っていただいたときと違ったことだったり、同じだなと思ったことはありましたか?
秋山先生:僕が初めて練習に来るまでっていうのは学生指揮者が振ってくれてたんだよね。ある程度の下練習はしてくれてたじゃない。最初にベートーヴェンの序曲のアレグロのところなんてビシッと合ってたじゃない。前にシベリウスやったときなんかは細かいところがすぐにバラバラになっちゃってね。今回はバッチリいってるじゃんっていうのが僕としてのリハ第1回目の第一印象。こんならうまくいくぞって思ったんだよね。最初からこれだけできれば、あと何回かリハーサルあれば十分いけるぞっていうのは楽しみにしてるところ。
学生指揮者:ありがとうございます。
ーメイン曲「オルガン付き」についてー
学生指揮者:次に選曲の話に移りたいんですけれども、先生は選曲の際一貫してサン=サーンスの「オルガン付き」を推してくださっていましたが、その理由だったり意図だったりというところはございますか?
秋山先生:ベートーヴェンとかブルックナーとかはよくやってるじゃない。サン=サーンスはあんまりやらないよね。
学生指揮者:7年前にやってからは、演奏していないですね。
秋山先生:でしょう。で、会場が京都コンサートホールとザ・シンフォニーホール、両方ともパイプオルガンがあるから、どうせやるならパイプオルガン使えばいいじゃないって。
学生指揮者:なるほど。オルガン以外の話でも、3管編成のシンフォニーって、それこそコロナ禍で立て直しの時期というのもあり、なかなかそういう大きな編成のものができていなかったんですけど。そこも含めて勉強になる回だなと思って。
秋山先生:やっぱり管楽器はね、2管だとそんなに難しいことはないじゃない。3管だと音程をピシッと合わせるのなんかも難しくて、でもそこは絶対クリアしないといけないわけだよね。そういう意味でも3管編成でやって勉強になったと思うんだよね。
学生指揮者:我々がここ数年で演奏してきた曲の中で、前回フォーレをやる機会はあったんですけど、それに続けてまたフランスもののシンフォニーに取り組めることになって。それまでは逆にフランス人作曲家の作品に触れる機会がない状態が続いていて、なかなかドイツものとはまた違うフランスものの響きの作り方にもまだ課題があるような気がしているんですけれども。ドイツものとははっきり違ってこうしないといけないというポイントはありますか。
秋山先生:やはりドイツもの的ながっしりした重さや長さはフランスにはないから。楽器は全部違うじゃない、管楽器が特に。だから、音色の違い。今回やるサン=サーンス(交響曲第3番「オルガン付き」)なんかは、他の曲よりは重いほうだよね。サムソンとデリラの「バッカナール」なんて皆軽いからね。僕が初めて振ったドイツのオーケストラが、ベルリンのラジオのオーケストラ(ベルリン放送交響楽団)だったんだけどね。ベルリオーズの「幻想交響曲」をやったの。これがね、重いんだよ。
一同:(笑)
秋山先生:冒頭も全部重いし、べたべたなの。特に2楽章はさ、軽い優雅なワルツじゃない。これが始まるとさ、誰かが’’eins, zwei, drei, eins, zwei, drei !!’’って。軍隊の行進みたいに。
一同:(笑)
秋山先生:それで、「この前はいつやったの?」って聞いたらさ、譜面に書いてあるの見て、「37年前です」って。(笑)誰もそれ以来弾いたことないんだって。びっくりしちゃったなぁ。しかし、断頭台(4楽章「断頭台への行進」)は立派でした。(笑)
総務:世界中のオーケストラを指揮されている秋山先生ですが、他の国に比べると日本のオーケストラにはどのような色があると思われますか?
秋山先生:そうだね、イギリスなんかもそうなんだけど、伝統的なクラシックの作曲家というのはあまりいないじゃない。現代や近代になったら出てくるけど。その分オーケストラがフレキシブルなんだよね。昔からこうやっていますというのがないから。日本でもN響がそろそろ90年とかでしょう。200年も前からやってるわけではないから。だから、日本のオーケストラでは、色んないい要素を取り入れて、それぞれの国の色を出すのは易しいというか、可能なわけだよ。使い分ければいいんだから。それを指揮者が心得て、例えばフランスものだったらフランスものの色、ロシアだったら帝政ロシアの色って。当時は大砲なんかでも旧式のでさ、ミサイルなんてないわけだから(笑)その使い分けの、1番の可能性のあるのは日本のオケだって、向こうの人も言うんだから間違いない。だからそれを売りにすればいいんだよ。このオーケストラは何色っていうんじゃなくて、1つのオーケストラを何色にでもできる。「あなた色に染まります」みたいなね(笑)そうしたら絶対面白いと思うんだよね。このころは色んな指揮者が来るようになったけど、そのたびにN響なんかもやっぱり音色が変わるし。指揮者の色に染まるっていうのは、オケとしてのカラーがなくなっちゃうんじゃないのっていう人もいるけど、音色の変化として音楽がつくれるっていうのが日本のオケの特色なのかなって思うね。だから、このオーケストラ(京大オケ)もフランスものやったら、本当に軽い奏法で。出来たらフランスの楽器使って。(笑)
学生指揮者:先ほどおっしゃったような、ドイツのオケでベルリオーズがめちゃくちゃ重たいとか、確かに日本だとあまりそういう印象はないですね。
秋山先生:だから、使い分けが少しずつ出来てきているということだね。例えばドイツだけに留学して、ドイツのオーケストラに慣れてきちゃった人が帰ってきたら、フランスものは弾きにくいなんて言うんだよね。(笑)だから、ヨーロッパの色んな国まわって、どの国のオーケストラがどんな色を出してるかというのを見てほしい。ベルリンフィルみたいな伝統的なオーケストラもそれはそれでいいんだけど、そういうオケはもうインターナショナルになってるから、作曲家の国によって音色を使い分けるんだけど。田舎の方のオーケストラ見に行って、どういう音鳴らしてるかっていうのを見ると面白いよね。フランスなんて、田舎の方に行っても、軽やかでふわっと香水の香りがするような演奏をするよ。ロシアはボルシチの匂いがするね。
一同:(笑)
総務:今ではインターネットで色んな作曲家の曲の色んな演奏が自由に見られるようになりました。
秋山先生:学生なんかで、YouTubeで聴いちゃってさ、こんなスマホのスピーカーにもステレオにもならないようなので聴いて、それで「これが本当の音だ」なんて言ってるやつもいるからさ。馬鹿者!ってさ。(笑)本当の生音聴けよってね。
総務:やはり本物にきちんと触れるのが大切ということですか?
秋山先生:そうだね。昔僕が学生の時なんて、外国から来るオケなんてほとんどなくてさ。最初に来たのは、アメリカのNBCシンフォニー。大きなブルドーザーがゴーッと音を立ててるような地響きがしたんだよね。日本のオケがまだ下手くそな時代だったからさ、度肝抜かれたけど。ロシアのオケが来てショスタコーヴィッチをやった時なんて、びっくりしたんだけど、まだまだ楽器がボロボロなのね。ホルンなんかも継ぎはぎだらけになってて、指が当たるところがすり減って穴が開いちゃうんだって。それでもね、いい音を出すの。日本だったらあんなボロの楽器ではぼへぇ~としか鳴らないよ(笑)コントラバスの振動なんかも、お尻にびりびり伝わってくるの。でもね、やかましい汚い音じゃないんだよ。本当の、太い良い音でそれが出てる。全員がそう吹いてるから、圧倒的なボリュームなんだよね。日本なんか、8小節でもくたばってるのに。
一同:(笑)
秋山先生:だから、オーケストラのいい音を作るには、いい楽団のいい音をできるだけ生で聴くことだね。今は学生券なんかがあるから、1万円も2万円も出さなくて済むでしょう。僕らの時なんかはね、(コンサートの)もぐりをやったわけ。先生の後くっついて入っちゃってさ、トイレの中に隠れて開演を待つわけ。切符なんか買えないからさ。それで知らんぷりして天井桟敷、お客さんのちょっと少ないところに潜り込んでさ。でも時々つかまるんだよね。僕も(こっそりコンサートを聴く)常連でさ、もぎりのおじさんやおばさんに「また来たか!」なんて言われて。だけど、ずっとあとで(そのホールに)振りに行ってさ、そのおばさんたちがまだ現役でいたりしたわけ。「その節はお世話になりまして」なんて言ったら、「おお、偉くなったな」って。
一同:(笑)
総務:生で聴くという点だと、オルガンの音色を生で聴いたことのある団員は少ないと思うのですが、「オルガン付き」で使用するパイプオルガンにはどのような印象を持たれていますか?
秋山先生:やっぱり電子オルガンとは違う、空気で音を出す楽器だからね。管楽器にリードがあるみたいに、オルガンは木のリードではないけど、金属のリードじゃない。ハーモニカと一緒だからさ。だから、日本じゃ都会のホールには増えたけど、地方にはほとんどないからね。大阪かどこかでサン=サーンスの3番をやったときに、バーンとオルガンがフルでC-durが鳴らすところ(2楽章後半)、あるでしょう。そこでオルガンが鳴りすぎるって書かれたことがあるんだけどさ。鳴りすぎてるんじゃない、耳が慣れてないだけだよって。だからさ、普段聴いてないんだよね。ヨーロッパだったら、そこらじゅうに教会があるから、オルガンコンサートなんかしょっちゅうやってるよね。特に西の方だったら、残響が5秒くらいあるようなちょっと多すぎるんじゃないのっていうくらいの響きをフルに流しながら、タイミングで音が濁っていかないようにっていう弾き方を彼らは300年前から研究してるんだよね。やっぱりパイプオルガンは、サン=サーンスをやる人は聴いた方がいいね。
ー中曲「ハムレット」についてー
学生指揮者:それではリストの交響詩『ハムレット』について。演奏機会も聴かれる機会もなかなかない曲だと思いますが、どのようなところに魅力があるとお考えでしょうか?
秋山先生:今言ってくれたように、ほとんど演奏されることがないよね。この曲は13曲ある交響詩の第10番じゃない。その中でも3番の「レ・プレリュード」、あれはもう世界中どこでも演奏会でやってるような曲だよね。楽曲としてもとってもまとまりがいいし。でもそれが10番になると、ある種精神分裂的な感じのする構成だったり、取っつきにくいような曲になるよね。不思議、不可解な音楽の運びの面白さというのが出てくるわけだ。皆にも「こんなのやだ!」なんて言わないで、譜面に書いてあることをまずやってくれれば曲になるわけだからさ。技術的にも弦楽器、管楽器ともに覚えといてほしいこともたくさんある曲だしね。服装でも、最もオフィシャルな服として燕尾服があるじゃない。女性だったらイブニングドレスなんかね。音楽でもそういうのがある部分では大切なんだよ。これはこういう弾き方じゃなきゃダメなんだっていうね。
学生指揮者:そうですね。演奏上のある種の常識みたいなところは楽譜から読み取るのは難しく、実際の演奏を聴いたり、経験を積まれた方に教えてもらったりしないと身につかないところではあると思うので、引き続き徹底して見ていきたいと思います。
学生指揮者:先ほども出ましたが、「ハムレット」はプロも含めて本当に演奏されることのない曲ですよね。日本での演奏記録もあまり見つかりませんでした。
秋山先生:(指揮者デビューした)60年前から数えても、1,2回やったかそこらじゃないかな。日本とアメリカで1回ずつ。あとはやったことない。誰もプログラムに組んでくれないからね。
一同:(笑)
学生指揮者:確かに、1度聴いただけだと「なんだこれ」ってなってしまう曲ではありますよね。とにかくずっと暗いし。
秋山先生:最初に「憂鬱にやれ」って書いてあるしね。
学生指揮者:ネガティブな単語が楽譜のあちこちに書いてありますし、使われる和音にしても長三和音のような聴きやすい和音がかなり少ない印象で、短三和音だったり減七だったり増三和音だったり……。そういう意味でも、演奏してる側としてもかなりつかみづらい印象はなんとなくあるのかなという感じはしますけれども。その中でも、音程など合わせられるところはきちんと合わせて、うまく物語として表現できるようなところまでは行きたいなと思っています。
秋山先生:オフィーリアのテーマというのがあるでしょう。華やかで美しいオフィーリアではなくて、ネガティブな考えにばっかり進んでいっちゃいそうな運びだよね。そういうイメージでリストが書いたとしたら成功だと思うけど。やってる方はたまんないよね。
一同:(笑)
総務:一見聴衆受けのよくなさそうな曲を取り上げるときと、所謂有名曲を取り上げるときで、先生の心持は違うのでしょうか?
秋山先生:例えばその原作があるとすれば、その雰囲気を引き出せたらいいなというのはあるよね。さっきおっしゃったような(物語として成立するような)表現のしかたっていうのはちょうどぴったりだと思うんだけどね。
ー前曲「『プロメテウスの創造物』より序曲」についてー
学生指揮者:ベートーヴェンの『プロメテウスの創造物』にしても、他の序曲の「コリオラン」だったり「エグモント」だったり、「レオノーレ」とか「フィデリオ」とか、それらに比べるとこちらも演奏機会の少ない作品で、当団の演奏会記録を調べたところ約50年ぶりとのことだったんですが、この作品にはどのような印象をお持ちですか?
秋山先生:今言ってた3つ4つの有名どころの序曲、これらは何十回、何百回とやってるような曲だけど、(『プロメテウスの創造物』の序曲も)やっぱりベートーヴェンの構成力のしっかりしたところやハーモニーの確かさというか、変にぐちゃぐちゃになるところはないじゃない。だけど、僕が思ったのはね、プロメテウスってギリシャ神話の火の神様だっけ?こっそり全能の神ゼウスに内緒で人間に火をあげたって、ゼウスから怒られるわけじゃない。でも、怒られるところはこの曲の中ではほとんどないじゃない。そこんところをどう表現したらいいんだろうっていうのは思うんだけどさ。こっそり逃げたのかななんて(笑)もし逃げたんだとしたらゼウスは追っかけなかったのかなって。(笑)想像しかできないんだけどね。どう思う?(笑)
学生指揮者:うーん、確かに。少なくとも、ずっと長調の曲ですよね。たまにハ短調の部分があるくらいで。
秋山先生:減七なんてないしさ。
学生指揮者:それこそハムレットとは対照的な。(笑)
秋山先生:どうだろうなぁ。ベートーヴェンはギリシャ神話というものを捉えるときに、そんなに深刻には考えなかったのかなぁ。「フィデリオ」とか「レオノーレ」とかは、オペラからの抜粋じゃない。これらはオペラの筋書きからくる力強さとか悲惨さ、悲しみなんかを上手に使い分けた構成ができてるから、納得いくと思うんだけどね。『プロメテウスの創造物』は、小さいクエスチョンマークが3つくらいついちゃうよね(笑)
学生指揮者:プロメテウスをテーマにした作品って他にもあって、それこそリストも書いてますし、スクリャービンの5番なんかにもプロメテって題名がついてると思いますけど。そのあたりと比べても、底抜けに明るい曲ですよね。
秋山先生:後世のそういう人たちがベートーヴェンのを聴いて、これじゃあ物語の中身が見えないよってね。
学生指揮者:そうかもしれないですね(笑)
秋山先生:幼稚な想像だけどね(笑)
総務:古典派の曲は、ロマン派以降のリストやサン=サーンスに比べて圧倒的に曲想・イメージの記述が少ないように感じるんですが、その中でベートーヴェンらしさを出すにはどういう風にしたらいいのでしょうか?
秋山先生:そうだね。例えば序曲にしても、オペラの中からテーマを取り出して、それを組み立てていくつか合わせてってするんだけど。モーツァルトやヘンデルもオペラを書いてるよね。ベートーヴェンは「フィデリオ」ってオペラを書いて、あとは劇音楽で、「エグモント」とかあるじゃない。芝居のための曲をいくつか出してね、それの序曲。でも、『プロメテウスの創造物』はそうじゃない。いい意味でも確固たるC-durの和音が鳴り響いたり、最初はサブドミナントで始まるじゃない。
学生指揮者:そうですね。サブドミナントがF-durで、それの属七の、さらに第三展開形ですね。そこも自分は面白いなと思っていました。
秋山先生:そういうところだけで、激しいものを表現したかったのかなとは思うんだけど。だけど、冒頭のメロディーなんか、ちっとも怖い音楽じゃないもんね。穏やかで平和な天国の音楽が始まったみたいな感じで。
学生指揮者:今日もちょうどご指導いただきますが、冒頭4小節はこだわりどころなのかなと思いますね。こちらの練習でも丁寧に音程を見たりしたのですが、まだ問題はあると思いますので、忌憚なくご指導いただければと思います。
秋山先生:あとね、スタッカートのマークって、日本じゃ音を短くって教わっちゃうんだけどさ、発音をはっきりって意味も含めてるんだよね。音の立ち上がりを非常に明確にって。だから、ベートーヴェンの場合はさ、八分音符にスタッカートがついてるのなんて普通で、四分音符にもあって、二分音符にも、全音符にもついてるんだよね。皆短く弾いちゃうんだけど、「全音符でなんで点があるの、間違いですよね」って人がいっぱいいるんだよね。全音符にスタッカートがつくわけがないって。そうじゃなくて、2つ並んでたら、一音目はもちろん二音目の発音をちゃんとしないとべたべたした感じになっちゃうから、切り目を入れて、一発目と同じようにはっきりついて出ろっていう意味だぞっていうのを、まだ日本のオケのプロの人でもたまにわかっていない人がいたりするからね。というのはね、ベルリンフィルの人に聞いたんだけど、カラヤンが練習中に「音が短い!響きをきちんと見せてから音を消せ!」って言ったら、「だってスタッカートマークがありますから。」って。「君はそのスタッカートの意味を知らないのか?君の音楽学校の先生は誰だ、スタッカートについて教えてないのか?」って聞いたら、「教わったことありません!」なんて言って、じゃあ「その先生呼んで来い!」って言われたんだって。
一同:(笑)
秋山先生:カラヤンなんてもう帝王だからさ、なんでもOKなんだよね、そういうの。ベルリンの音楽大学の先生がクビになりそうになったんだって。
学生指揮者:確かに、カラヤンの振る『プロメテウスの創造物』は、冒頭がかなり重く、音価をしっかり取ってという演奏で、自分はそれになじんでいて。それでいざプロメテウスをやることになって最初の練習で振ったときに、皆相当短くて。確かにそういう演奏は、特に古楽器なんかでは多いですけれども。皆そっちでなじんでいるのかなと。しかし、少し違和感はあったので、もう少し長くしてくれと言ったんですけど、癖が治らず、先月秋山先生に見ていただいたときに、「あ、やっぱり長いんだ」って(笑)
秋山先生:古楽器だってさ、当時は放送もなきゃCDもないしレコーディングもないし、各地方でそれぞれ勝手にやってたんだよね。うんと長くしてもいいし、短くしてもいいし、バラバラだから、どれが正しいなんてわからないんだけどね。
ー秋山先生からのメッセージ
学生指揮者:当団に求めること、期待することはございますか。
秋山先生:さっき言ったようなことだね。いろんな生の演奏会を聴いて、固定観念に囚われすぎず、フレキシブルに。曲に関しても、いろいろ実験してみるっていうか、色んな演奏方法があるよね。
学生指揮者:お聴きいただくお客様に向けて、メッセージをお願いいたします。
秋山先生:伝統ある京都大学交響楽団、自分たちも一所懸命切磋琢磨している段階ですけれども、どこの国でもオーケストラにとって「完成」というのはないわけだから、もちろん完成を目指すんだけれども、これからも歩みを止めず精進します。
学生指揮者:団員に向けてのメッセージも、お願いします。
秋山先生:今言ったのと同じだよ(笑)たった4年間しかいないわけだからね。他の大学オーケストラなんかでは、「楽しみでやってるんだから、細かいこと言わないでね」ってとこもあるんだけど。アマチュアや学生オケを振るときも、プロオケと同じレベルの要求をするね。
総務:「秋山先生は学生の我々にも全力でぶつかってくださるから、先生の指揮で演奏するのがすごく楽しい」と言っている団員もたくさんいました。
秋山先生:それは嬉しいね。適当にやってくださいって言われるのが一番嫌なんだよね。
総務:その真摯さっていうのが音楽だけでなく、以前「毎日本番と練習と楽譜の勉強の日々で、ほとんど休暇がない」とおっしゃていたのを聞き、学生としてもその謙虚な姿勢は本当に勉強になるなと思っております。
学生指揮者:実際、先月もどこかのパートの主席奏者が「先生の楽屋にご挨拶にいったときも、スコアを読まれていた」というのを聞いて。自分も読まなきゃなって(笑)
ー定期演奏会に対する意気込みー
学生指揮者:最後に、この定期演奏会に対する意気込みを、まとめるような形でお願いできたらと思います。
秋山先生:それぞれの曲を、あちこちボロを出さないようにまとめあげる。それしかないんだけどね。
学生指揮者:我々としても、妥協なく、練習に努めてまいります。ご指導の方、これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました!
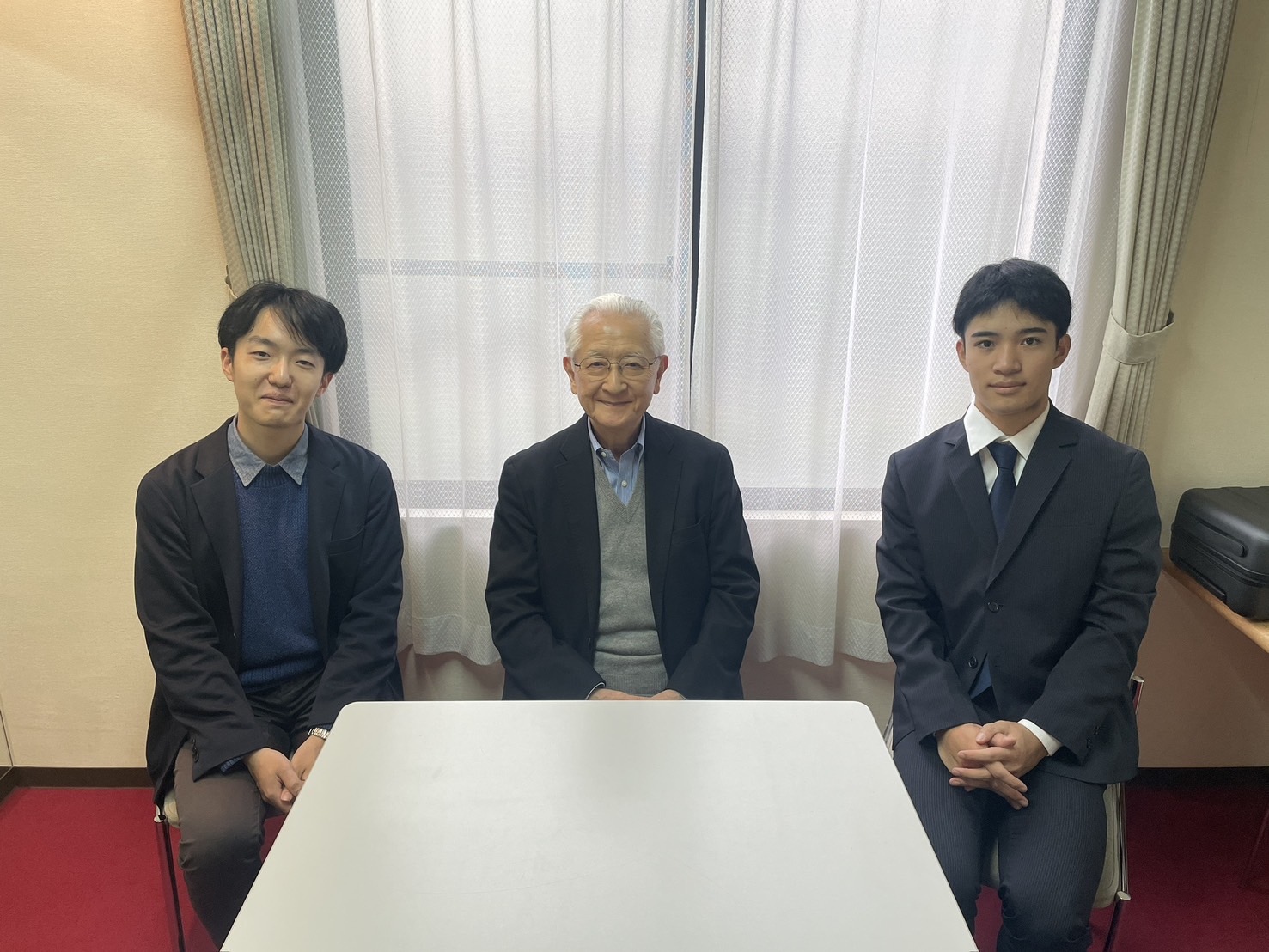
※カッコ内は編集者注
